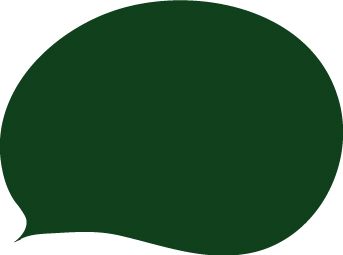季節によって水やりは変る
春、秋はもっとも穏やかな季節なので普通
の水やり。
乾いていたらあげる。教科書通りのやり方です。
完全に根が活着すれば乾かし気味に水やりをして、
週に一、二度まとまった雨が降るようならほぼ放
任で済みます。
ただし晴天ばかりが続き乾燥がひどい場合は何日
に一度というやり方ではなく、花や茎、葉の状態
を観察しながらの水やりをする。
花や茎がお辞儀していたり葉がしおれているよう
なら水が足りていません。
限界だというサインなので次からはしおれる前に
やっておきましょう。
忙しいのが夏の本番。
植えたばかりの花は毎日やってもいいくらいです。
夏はすぐに乾いてしまうのでたっぷり過ぎるほど
やってください。
ただ日陰や半日蔭にいる植物には多少手を抜いて
も大丈夫。
夏だといっても乾きは遅いはずです。
やる時間帯はなるべく午前の早いうちがいいでし
ょう。
真夏となれば9時にはもう30度超えです。
高温になる1時間前までにはやっておくのがいい
です。蒸されますからね。
ホースリールで水をやる時の注意点。
ホースの中の水がお湯となっています。
お湯をかけると蒸されるどころではないので、冷
たい水が出るまで待ってからあげてください。
のんきにいられるのは冬の水やり。
ほぼ雨だけで凌げます。
ただし冬でも水を必要とする植物には、間を置い
て定期的にやらなくてはいけない。
冬の水やりをサボれば春先の花に影響します。
家庭で育てやすい果樹にブルーベリーがあります。
これは冬でも水を欲しがる。水をやらないでおく
と収穫するほどの量は実りません。
実があまり出来なかったというのは、もしかする
と冬の水やりが原因なのかもしれないのです。
冬は気温がぐっと下がっていますからやる時間帯
は午前中の気温が上がった頃。
夕方にあげるのは勧めません。
その晩に根ごと凍ってしまう。知らない間にダメ
ージを与えてしまうのが冬場です。
冬は水やりはせわしくなくてもやることはちらほ
らあります。
春先のために鋏を入れないといけない、寒肥えな
んかも一番寒い1月末から2月上旬です。
これは次の肥料のページで説明します。
ニッポンには四季がありますからね、寒い暑いの
変化があるなら水やりも変わります。
乾き具合を見ながらやること。
夏のような水やりを一年通してやってしまうこと
がないようご注意ください。

上はよく見かける典型的な水やりのシーンです。
しかしデリケートな花には勢いよく上からかけて
はいけません。花が壊れます。
夏場なら水滴がレンズとなって火傷を起こす。
葉からカビ病が発生することもあり、花に水滴が
残り蒸れる、変色する、傷む、いいことなし。
雨は上から降るじゃないかと、それは自然の摂理
なので仕方のないこと。雨の日は空も曇っていま
す。火傷を起こすこともない。それに雨水は豪雨
じゃなければやさしい水滴です。
人の手でやる時はなるべく花や葉が傷まない方法
を取らないといけません。
真上からの水やりはたくさんやったつもりでも株
元には十分な量となっていません。
たっぷり水を吸わせるには直接株元にやります。
コツは水量を下げてゆっくりやる。じわじわと土
に水がしみ込みます。
しみ込む速度が落ちるまで何度か繰り返す。
たっぷりやるとはこのやり方を指します。
仮にバケツ一杯の水をやったとしてもすべての水
を花が吸い上げるわけではありません。
根が拾える量は僅かです。地面に広がり乾燥して
なくなる量の方が圧倒的に多い。
なので十分に足る水が必要なのです。
地中に深くしみ込ませ、べたべたになるくらいあ
げてください。
ラグラス
イネ科の一年草
これなんかは上からかけてしまうとべちゃっと倒
れてしまいます。
株元へそっと水やりしないといけないので、ホー
スよりジョーロです。株元にやりやすいから。
もちろん先っぽの口は取りますよ。ハス口は草花
の水やりでは要らないものです。

因みにこの草花の特徴は、なんといってもこのふ
わふわ感。花の観賞は4月~7月。長いですね。
日なたを好むとありますが、まぁ午前中陽があた
れば大丈夫でしょう。
高温多湿に弱いので乾かし気味に水やり。
水はけの良い土を好む。やせ地でも育つ。という
ことなので砂地でも問題ない。
草丈20~30センチ程度。改良を加えた矮性種とい
うことなので高性種となればもっと背丈が高い。
根付けば放ったらかしでもいい手間いらず。暑さ
にも強いと。
花らしくないところが良く、アクセントには丁度
いい。寄せ植えでは名脇役となるはず。もしかす
るとこれの方が目立つかもしれません。
切り花でもドライフラワーでも楽しめる。
※矮性種とは本来の姿より小型に作られた品種を
いいます
このバケツの寄せ植えは施主が作ったものです。
ここの施主もこれまで本格的なガーデニングをし
たことはありません。
まったくの素人がこんなかっこいいコンテナを作
っていたのでちょっと拝借しました。
ガーデニングは基本さえわかればあとは応用と組
み立て。
コンテナの寄せ植えは同じような性質を持つ草花
を植えるのがセオリーです。
水を欲しがるものとそうでないものとでは相性が
悪いので、この先どちらかが調子を落とします。
この二つは同じペースで水やりが出来るため問題
なく育っていくわけです。
「水は毎日やらないといけないんですか?」
ビギナーが一番先に知りたいのがこれです。
私もそうでした。
草花を始める方、みんながここからスタートした
んだと思います。
「湿地性の植物、つまり水際で自生する植物以外
は毎日やり続けると根腐れを起こします」
植物への水やりはやり過ぎないこと。
といってもこれは一度にやる「量」の話ではあり
ません。
やる「頻度、回数」の話です。
ここをよく間違えるのです。
やり過ぎないように=ちょろっとやって終わり。
これでは砂漠に咲いてる花と同じ。
やる時はたっぷりとやります。しつこ
いくらいやっても問題ありません。
ただし、、一度たっぷりやったら土が乾くまでは
やらない。
人もペットもお腹一杯食べたら間を置きます。
土は植物にとって胃袋だと思ってください。
水やり三年。聞いたことありませんか?
きちんとした水やりが出来るまで三年は掛かるという
例えなんですが、しかし枯らさずそこそこ花を咲かせる
コツはそんなに難しいことではない。
奥深いところまで行く人が三年どころか十年でも迷走します。
植物は水やり一つで花が変わります。
ちょっとしたコツさえ掴めば普通に育ってくれるんです。
植えたばかりの花はひと月ほどで根が活着します。
根が張るほど地力が付きます。
根に力が付いてくれば多少水やりが遅れてもそう
心配することはありません。
植物は余分な酸素や蒸気を葉から蒸散させるんで
すが、
水不足を感じたら気孔を閉じてその蒸散を防ごう
とします。
防衛本能が働くため水が切れた途端枯れるなんて
ことはまずありません。花瓶の花とは違います。
根が成長するほど体力が付いてくる。
一年目だけは油断しないように。
根が増えてしっかりと根付くまではちゃんとした
水やりが必要です。
繰り返しますが、やる時はたっぷりやる、
次やる時は土が乾いたあと。土の表面が湿ってい
たらやらない。
水やりはこれが基本です。
植物は吸い上げた水を葉から蒸散します。
なぜ蒸散を続けるかといえば一つには葉
へ栄養を送るため。
土壌の養分は水と一緒に運ばれます。
土から拾える養分は微々たるものです。
そのため大量の水を送り蒸散させる必要
があります。
二つ目は蒸散によって体温を下げたり、
周囲の温度を冷やすためです。
特に夏場の水やりは大切ということにな
ります。
夏場の灼熱の中でも生き延びることがで
きる雑草とは違い、植えたばかりの樹木
や園芸種の草花は人の手による適度な水
やりが必要です。
光合成の話
むかし授業で習ったと思うんですが、皆さん詳し
くまでは覚えていません。
私もこの仕事に就くまでは記憶から消されていた
ので人のことは言えないんですが・・、たぶん授
業中寝てたんでしょう。
この光合成、植物を知る上では知っておかないと
いけない話です。
そもそも光合成とは何か。
植物がこれをしたおかげで地球上すべての動物が
誕生しこれまで生き残れたのです。
二酸化炭素を取り入れ酸素にして吐き出したとか、
そんな話をするつもりはありませんが、
とにかく生き物すべてが必要とする酸素を、地球
の隅々にまで供給してくれる命の恩人なわけです。
で、植物はいつ光合成するのかというと、もっと
も活発になる時間帯は午前中。これを知っておい
てください。
午前の早い時間は気温が低く、光の強さが優しい
ため効率よく光合成が行えます。
光合成をするには陽の光だけじゃなく水の力も不
可欠です。
成長期の植物にとってその時間帯は水を吸い上げ
る力が強く、どんどんとエネルギーに変えていき
ます。
酸素はその過程で要らないものとなってそれで外
へ吐き出すのです。
何が言いたいかというと水やりは午前中の朝にや
りましょうと。
光合成にもっとも適した温度は25℃前後だといい
ます。40℃近くになれば光合成が著しく低下しま
す。
周囲のコンクリートは夏場60℃にもなりますから
40℃を軽く超えます。
つまりもっとも光合成率のいい時間帯にやればす
くすくと元気に育つわけです。
夕方が涼しいからとその時間帯にばかりやり続け
るのは、光が弱く光合成の働きが悪くなり、茎や
枝が変に徒長してしまいます。
葉からの蒸散が少ないと溜めこんでしまうのです。
もちろん朝以外やってはいけないということでは
なく、たまにやる分には問題ありません。
ただ夕方やるのを「日課」にするのは避けた方が
いい。
正常な育ち方はしない。花つきも悪くなる。じめ
っとした土は雑菌が好み病気の原因になります。
なので日課にするのなら朝なんですよ。
水やりについてはこんなところです。
やり過ぎは駄目だといってもまったくやらないで
は枯れてしまう。
厳しい育て方を勧めているのではありません。適
度に乾湿の差を付けてやればちゃんと根を伸ばし
暑い夏を乗り切れる地力が付きます。
文字にすると難しそうですが、やってみると案外
二週間ほどでコツを掴めます。

庭仕事をしていくうちに「水はけが良く水持ちの
良い土」というような話をこの先嫌でも耳にする
ことになります。
排水性と保水性の話です。
水がきちんと抜けて、なお水持ちのいい土が良い
土の条件。
よーく読み返すとちょっとおかしな話をしている
と思うかもしれません。
水が抜けても水持ちがいい?「はぁ?」。
これは団粒構造に係わり話が長くなるのでここで
は割愛しますが、分かりやすく言えば濡れた雑巾。
水に浸けた雑巾をぎゅっと絞ると水滴がぼたぼた
と落ちる。
この状態が水はけです。
しかし雑巾は濡れたまま。すぐには乾きません。
これが水持ち。
水はけの良過ぎる土は短時間ですぐに水が抜けて
しまいます。
根腐れしない土ではあるけれど、水やりの頻度が
多く難しい土なのです。
なので水持ちのいい土を作るわけです。
これが団粒構造に係わってきます。これについて
は土のページで説明します。
花瓶のように水を溜めたままじゃいけないのかと、
そんなことをすれば雑菌が増殖し根にダメージを
与えます。
乾かしたり湿らせたりの乾湿の差を付けなければ
根が呼吸出来なくなります。
根腐れはいろんな原因で起きるんですが、水を絶
えず与え続け次々と足してしまっているのが最た
る原因だといえます。
で、基本が分かった上での話です。
草花は多湿に強いものと乾燥に強いものとがあり
ます。
多湿に強い植物といえば、日陰でもよく育つ植物。
逆に日陰が苦手で陽の光を好む植物は、だいたい
が多湿を嫌います。
つまり乾かし気味にしないと正常に育たない。
花屋に行って圧倒的に多いのは日なた向きの草花
です。
中でも乾燥に強いのはラベンダー、ローズマリー、
タイム、グラス系など。ハーブ類に多い。
いったん根付いてしまえばしょっちゅう水をやら
なくても問題なく育ちます。
極端な話、完全に根づけば夏場以外は雨だけで凌
げる体力を持っている。
といっても水が嫌いってことじゃありません。
ボリュームをどんどん出したければ乾いたあとで
の水やりを続ければいいのです。
他のよりワンテンポ置いて乾かし気味に育てる。
一年目の夏場を正常に無事越すことが出来ればほ
とんどもう大丈夫。
難しくはありません、水がすぐ乾く夏だけは水切
れに注意すること。
この丘は可児市の花フェスタ記念公園の中にあり
ます。
うちの施主の中にも行ったという方はけっこうみ
えました。有名な植物園です。
なにが有名なのかというと薔薇。
十万本でしたかね・・、とにかく相当な数の薔薇
を地植えしているので全国でもトップクラスの薔
薇園なのは間違いない。
むかし薔薇のことを少し勉強したかったので年パ
スを買って随分通ったものです。
この園の中で目を引いたのがターシャの庭を模し
た庭です。
今でもあるのか分かりませんが、当時は本格的な
イングリッシュガーデンを作っていました。
作ったのはボランティアらしく、その中に名うて
のガーデナーもいたという話です。
今はもっとよくなっているかもしれないし、逆に
荒れているかもしれません。
15年以上前の話なので、このベンチもたぶん朽ち
て今はもうないでしょう。
花好きな方は一度遊びに行ってみてください。歩
いている職員にあれこれ聞くと勉強になりますよ。
売店にある苗も豊富なので、薔薇に限らずレアな
草花も見つかるはずです。
土が乾いたあとでたっぷり水をやるのは
酸素供給のためでもあります。
たっぷり潅水する事で新鮮な酸素を送れる。
土が乾けば水を探しに根を伸ばす。
絶えず湿っていては根の伸びが悪いのです。